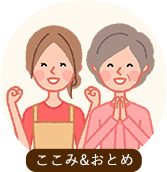公開日: |更新日:
【栃木県】多世帯同居、近居に対する支援や、多世帯同居、近居のメリット・デメリット|ココミテ
多世帯同居(近居)について
近居とは
それぞれの家庭が無理なく快適に生活できる場所に住むこと
二世帯(多世帯)住宅は、親世帯と子世帯が同じ家に暮らすことですが、近居とは、それぞれの世帯が、日常的に行き来できる距離にある、別々の住宅に暮らすことをいいます。近居はスープの冷めない距離とも言われることがありますが、実際、具体的な定義はされていません。近居については、移動手段が徒歩・車・電車かどうかを問わず、10~30分以内で行き来できる距離が理想という説や、車・電車で1時間以内の場所、という説もあり、家庭によって見方はさまざま。近居をする時はお互いの価値観をじゅうぶん考慮して、それぞれの家庭が、無理なく、快適に生活できる場所に住むことが何より大切です。
多世帯同居、近居のメリット
多世帯同居のメリット
多世帯住宅とは文字通り、複数の世帯が共同生活をするための住宅のことで、二世帯住宅も多世帯住宅の一部です。最近では、よくある二世帯住宅に加えて、親世帯と複数の子世帯が同居生活したり、親・子・孫の三世帯が住む三世帯住宅も増えていますし、夫婦両方の親世帯と同居するというケースもあります。
そんな多世帯同居のメリットは、住宅建設費の世帯あたりの負担額が少なくてすむこと、若い世帯でもマイホームを持ちやすいこと、光熱費削減になること、介護や育児、家事のサポートが受けやすいこと、相続税を減らせる可能性があること、個人住民税・不動産取得税・固定資産税が減らせる可能性があることなどがあります。「他の世帯との同居は煩わしそう」と考えてしまう人も多いのですが、快適な日常生活を送れるメリットから、長期的な目で見て経済的なメリットもあるため、まずは検討してみましょう。
近居のメリット
次に、近居のメリットを解説します。近居の良さは、やはり何かあったらすぐに駆け付けられるという安心感があることです。介護や育児が必要な時や、一時的に体調が優れない時など、近くに家族がいるだけで心強く感じるものです。また、近居は子世帯が共働きしやすい環境です。夫婦共働きが一般的になってきた現代、親世帯と子世帯では生活時間の差があり、二世帯同居の場合は早朝や深夜などにお互いに気を遣ってしまうことになりますが、同居はしていない近居であれば、このような心配はほとんどありません。夫婦共に帰宅時間が遅くなってしまう時などは、親世帯に子供の面倒を見てもらうこともできますので、安心です。さらに、記念日に三世代が集まりやすいこともメリットの一つ。普段は会う機会が少なくても、誕生日などの記念日や、お正月などの行事の時は家族で集まり、団らんを過ごせます。近居している親世帯が孫のお祝いに会いに来ることもできますし、子世帯がお正月やお盆などに気軽に挨拶に行くこともできます。大事なイベントに集まりやすいのも大きなメリットです。近居の場合は、お互いが行き来する際、渋滞に長時間巻きこまれてしまうということもありませんので、負担が減ると考えていいでしょう。
もし親世帯が亡くなり、実家の片付けをしなくてはならない時などは、遠く離れた地域に住んでいるとなかなか頻繁に足を運べず、作業や手続きなどで時間がかかり、心身共に疲れ切ってしまうこともあります。二世帯住宅では、どちらか一方の世帯の人が亡くなった時、人間関係や経済の状況によってはそのまま住み続けることができないケースもありますが、近居であれば、片方の家が空いた時に売却しやすいですし、賃貸住宅として活用するという選択肢もあります。また、子供が独立した時の住居として使うこともでき、それぞれのライフスタイルに合わせて、柔軟に資産活用することも可能です。
老後の資金を確保するため、田舎の持ち家を売却し、近居生活を始める家庭もあります。また、近居は出産や育児への不安を軽減し、介護しやすい環境づくりができるという観点から、国や自治体で三世代(親・子・孫)の近居・同居に対する支援制度が積極的に実施されているのもポイントです。リフォームや引っ越しにかかる費用が補助対象となるのが一般的ですが、補助要件や補助金額は地域によって異なりますので、近居・同居する予定の自治体に確認してみてください。
多世帯同居、近居のデメリット・注意点
多世帯同居のデメリット・注意点
多世帯同居の場合、世帯間の価値観や生活リズムの違いから、やはりお互いにストレスが発生してしまう可能性があります。親世帯と子世帯では、成長してきた時代背景や社会における感覚などが異なり、価値観や意識だけでなく、ライフスタイルにも差がありますので、料理の味付けや、掃除、洗濯の方法などの違いで、トラブルになってしまう場合があります。小さな不満でも、それが積もり積もって、深刻な問題にも発展してしまいます。また、子育て真っ最中で働きざかりの子世帯と、熟年を迎えた親世帯では、基本的な生活リズムが合わず、お互いがストレスを感じることもあります。親子は血でつながっていますが、夫婦はもともと他人同士。特に親世帯の母親が、子世帯の息子可愛さのあまり子世帯に干渉し過ぎてしまうと、うっとおしがられる可能性もあります。
また、お互いの世帯で共用で使用するスペースの多い従来の同居の場合は、家族一人一人が自分だけの時間や空間を確保することが難しく、プライバシーを確保することができない場合があります。お互いに言えることですが、良かれと思ってやったことでも、実際に相手の世帯がどう感じるかというのはまた別の話。何かが起こってそれを見てしまった以上、手や口を出さないことは非常に難しいものですが、こういった事態を避けるためには、そもそも見えないように工夫することも有効です。たとえば、親世帯と子世帯の家事空間をきっちりと分けるなど、メリットも多い多世帯同居では、お互いの関係を悪化させないための対策をしておくことも必要です。
近居のデメリット・注意点
近居には、同居のようなストレスがなく、ほど良い距離で家族が仲良く付き合って行けるイメージがありますが、近くに住んでいるからこそ起きてしまうトラブルもあります。家が近いため、些細な困りごとでも頻繁に呼び出される可能性がありますし、同居していればすぐに対応できることでも、近居の場合はある程度は行き来する手間があります。たとえ同じ町内で近居していたしても、何度も互いの家を往復するのは結構煩わしいものです。家が近いからといって、子が親を、親が子を頻繁に訪問する可能性もあります。同居・別居に限ったことではありませんが、、お互いがお互いのことを考え、思いやりを持って接することが何よりも大切です。
近居を始める前には、親が介護を必要とする状況になった場合、どのようにサポートをするか、きょうだい間でよく話し合っておくことも大事です。介護は突然始まるケースが多いので、きょうだいの誰かが近くに住んでいると、介護を押し付けられてトラブルになってしまうケースが多々あります。介護される親側の意思の確認も必要ですし、介護にかかる金銭や、介護の負担をどのように分担するか、事前に相談しておくことも必要です。
多世帯同居、近居の家作りの工夫
多世帯同居の家作りの工夫
多世帯同居では、限られた空間を有効活用しながら、二世帯またはそれ以上の世帯がほどよく交わり、快適に暮らせるような配慮が必要です。水廻りや玄関はシェアすることでゆとりのある広さを確保し、世帯間のプライバシーを守りつつ、ゆるやかなつながりを維持しましょう。
近居の家作りの工夫
近居をする際は、親世帯と子世帯が集まる時にも過ごしやすいよう、中古物件をリフォーム・リノベーションする人も増えて来ていて、将来的には同居や住み継ぎを考えて住宅選びをする人もいます。バリアフリー住宅で推進されている引き戸は、手荷物が多くても力を入れなくても開閉できますので、どの世代でも使いやすいのが特徴です。玄関や浴室、トイレの扉は、できれば引き戸にリフォームしておくといいでしょう。また、家族が集まる時に一番使うのは、リビングとダイニングです。誕生日会や年末年始などのイベントの際は、家族全員が集まってくつろげるよう、ゆとりのあるリビング・ダイニングにしておくとベストでしょう。料理や食器を運びやすいよう、キッチンからの動線も考えておきましょう。
栃木県の多世帯同居、近居に対する支援
栃木県内市町では、子育てしやすい環境づくりを推進するために、三世代同居や近居に対する経済的支援を行っています。三世代同居・近居(新築・増築・改築)の場合は、新築または、増改築した住宅が三世代同居または近居であることが要件です。詳しくは問い合わせてみてください。
栃木でおすすめの
注文住宅メーカー3選
スムーズな家事動線と
快適な空間を両立したいなら

-
家事の負担を減らす
動線&収納設計
女性ライフプロデューサーのヒアリングをもとに、オープンキッチンや最小限の移動距離を意識した動線設計を提案。収納にもこだわり、片付けやすい住まいを実現。 -
「ライフスタイルに合わせて、
住みやすい設備を自由に
選べる」
キッチン・バスルーム・内装建材など、10社以上・1,800種類以上の住宅設備を標準仕様で選択可能。フリーチョイスシステムを活用し、設備を暮らしに合わせて選べる自由度の高さが魅力。
断熱×太陽光発電で
エネルギーを活かしたいなら

-
高断熱×太陽光発電で、
省エネ&快適な暮らしを実現
断熱等級7に対応した高断熱構造を採用。外気の影響を受けにくいため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境を実現。さらに、太陽光発電を標準搭載し、光熱費を抑えながらエネルギーを効率的に活用 できる。 -
停電・断水時も安心!
災害時の備えにも対応
万が一の停電時には、太陽光発電+蓄電池で電力を確保し、普段と変わらない生活が可能。また、断水時でも約6日分の生活用水を確保 できるため、ライフライン確保にもつながる。
IoTで家電をコントロール!
スマートに暮らしたいなら

-
「IoTで家電&エネルギーを
管理し、快適な暮らしを実現」
アイ工務店のIoT住宅は、スマホやAIスピーカーで家電を操作でき、外出先からエアコンや照明のON/OFFが可能。また、分電盤に設置された電力センサーで家全体の電力使用状況をリアルタイムで確認し、無駄な電力を抑えて節電&家計管理にも活用できる。 -
無駄のない動線設計で、
ストレスフリーな暮らしを実現
家族の動きを考えた「おかえり動線」や「回遊動線」を採用し、生活の流れをスムーズに。最短ルートで移動できる設計により、家族の移動ストレスを減らせる住まいを実現。