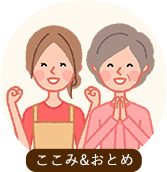公開日: |更新日:
建材を選ぶ時のポイント
注文住宅を検討するなら建材にこだわりましょう。建材次第で見た目に限らず日常生活の快適性が損なわれるからです。ただ、建材といわれてもなにがあり、なにがいいのかわからないことはいっぱいあります。まずは建材選びのポイントをチェックしておけば、理想の注文住宅に一歩近づけるのです。
断熱材選びのポイント
断熱材は「清浄な空気」「温度」「長持ち」に関係します。快適性と寿命に大きく関係するためこだわりたい建材のひとつですが、各種類の機能性やコストを考えて選びましょう。
グラスウールは安価だが断熱性能は普通程度、セルロースファイバーは高額で断熱性は特別高くないですが、防火性や防音性や環境面など付加価値はたくさんあります。
断熱材の種類
- 無機繊維系
- 木質繊維系
- 発泡プラスチック系
断熱材には大きく分けて上記3つの種類があります。無機繊維系はグラスウールとロックウールがあり、防音性や害虫に強い断熱材ですが、どちらも湿気に強くありません。ただ、グラスウールは断熱材の中でも料金がリーズナブルです。
木質繊維系はセルロースファイバーがあり、自然素材で無機繊維と比較すると基本性能がすぐれています。高い調湿性で結露に強いですが、料金は高額の部類で、リフォームには適していません。
発泡プラスチック系は硬質ウレタンフォームやフェノールフォームなどです。断熱性、省エネ、透湿性、耐久性に優れている断熱材ですが、高額なものが多く、燃やしたときに有毒ガスが発生するものもあります。
フェノールフォームは水に弱く、ビーズ方ポリスチレンフォームは熱に弱いなど種類ごとにメリットとデメリットがあるのです。
外壁材選びのポイント
外から見たとき外壁は建物のイメージを左右する建材ですが、種類により強みや費用も異なります。外壁を選ぶときは「素材」「色」「メンテナンスのしやすさ」「耐久年数」「周辺環境」「家のイメージ」を抑えておくといいでしょう。
色は天候や時間帯でも変化し、暖色は明るさや親しみ、寒色はクールでモダンのように印象が変わります。耐久年数やメンテナンスもまとまった金額が必要なため、将来の外壁塗装も前提として踏まえて選んだほうがいいでしょう。
外壁材の種類
- 窯業系サイディング
- 金属系サイディング
- 樹脂系サイディング
- 木質系サイディング
- モルタル
- タイル
- ALC
外壁材は主に7種類あり、耐久年数にも関わる防水性、防火、断熱、遮音、耐震性も重要視し、同時に意匠性にも注目しましょう。採用されるのが多いのは窯業系サイディングで、コストやデザイン性に優れて加工もしやすいタイプです。
金属系は水や凍害に強いですが、海が近くだと塩害、他にももらい錆や電蝕というデメリットがあります。樹脂系は木のぬくもりと断熱性の高さ、その分コストや水による腐食や偏食が弱点。
モルタルは耐火性とデザイン性の自由度は魅力ですが、ひび割れや汚れやすいのは弱点です。タイルは耐久性の高さは強みですが水に強くありません。ALCは軽く断熱性や耐火性に優れますが、防水性は弱く水が入ると劣化が進みます。
メンテナンス頻度は、樹脂系が10年~20年と長く、続いて金属とALCタイルが10年~15年、木質が7年~10年、モルタルが5年~10年、窯業が7年~8年が目安です。
屋根材選びのポイント
屋根材を選ぶときのポイントは「コスト」「デザイン」「耐用年数」です。屋根材は種類の違いでコストも2倍程度変わることもあります。コストで一番安価なのはトタンやスレートやガルバリウム。ただし、トタンは耐用年数が10年~20年程度で短いです。
デザイン性も種類で異なります。粘土瓦は日本家屋にぴったりで、アスファルトシングルもデザイン性が高いといわれているタイプです。また、屋根は雨や紫外線の影響を建物内で一番受けやすく、メンテナンス頻度も含めて選びましょう。
屋根材の種類
- 銅板(60年~)
- 粘土瓦(50年~)
- セメント瓦やコンクリート瓦(約30年)
- ガルバリウム鋼板(約30年)
- アスファルトシングル(20~30年)
- 化粧スレート(20~25年)
- 天然スレート(20年~)
- トタン(10~20年)
上記が主な屋根材の種類で、耐用年数の高い順に並べました。カッコ内は耐久年数の目安です。銅板は60年以上の耐用年数を誇り、サビにも強く、軽量で耐震性の高さと強みは多いのですが、価格は最も高く相場は1㎡あたり2万円以上にもなり、施工ができる業者も限られます。
トタンは耐久年数も低く、長く保って約20年。耐熱、防音性は低いですが、コストは最も安く軽く、耐震性も高いのが強みです。それぞれ強みと弱みがあるためその点を重視し、後悔しない屋根材選びをしてください。
栃木でおすすめの
注文住宅メーカー3選
スムーズな家事動線と
快適な空間を両立したいなら

-
家事の負担を減らす
動線&収納設計
女性ライフプロデューサーのヒアリングをもとに、オープンキッチンや最小限の移動距離を意識した動線設計を提案。収納にもこだわり、片付けやすい住まいを実現。 -
「ライフスタイルに合わせて、
住みやすい設備を自由に
選べる」
キッチン・バスルーム・内装建材など、10社以上・1,800種類以上の住宅設備を標準仕様で選択可能。フリーチョイスシステムを活用し、設備を暮らしに合わせて選べる自由度の高さが魅力。
断熱×太陽光発電で
エネルギーを活かしたいなら

-
高断熱×太陽光発電で、
省エネ&快適な暮らしを実現
断熱等級7に対応した高断熱構造を採用。外気の影響を受けにくいため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境を実現。さらに、太陽光発電を標準搭載し、光熱費を抑えながらエネルギーを効率的に活用 できる。 -
停電・断水時も安心!
災害時の備えにも対応
万が一の停電時には、太陽光発電+蓄電池で電力を確保し、普段と変わらない生活が可能。また、断水時でも約6日分の生活用水を確保 できるため、ライフライン確保にもつながる。
IoTで家電をコントロール!
スマートに暮らしたいなら

-
「IoTで家電&エネルギーを
管理し、快適な暮らしを実現」
アイ工務店のIoT住宅は、スマホやAIスピーカーで家電を操作でき、外出先からエアコンや照明のON/OFFが可能。また、分電盤に設置された電力センサーで家全体の電力使用状況をリアルタイムで確認し、無駄な電力を抑えて節電&家計管理にも活用できる。 -
無駄のない動線設計で、
ストレスフリーな暮らしを実現
家族の動きを考えた「おかえり動線」や「回遊動線」を採用し、生活の流れをスムーズに。最短ルートで移動できる設計により、家族の移動ストレスを減らせる住まいを実現。